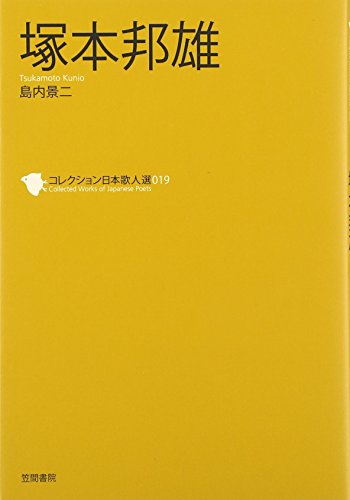感想『十蘭レトリカ』久生十蘭著〜とにかく楽しい!明治生まれの作家の書いたモラルなし、セオリーなしのドタバタラブコメディ。チャラ男と性悪お嬢様と大陸女の破壊的恋物語『心理の谷』は必読に値する。他7編収録。
-本書収録『心理の谷』について-
とにかく楽しい!の一言だ。久生十蘭の数多い短編のなかでも特にお気に入りの作品だ。
七日ほど前にJ・K・ユイスマンの『さかしま』を読んだあたりから、どうも鬱がちにどんより落ち込んでいたのだが、以前TVでオードリーの若林が重たい内容の本を読むときは、仕事に支障がでないよう、ワンピースと交互に読むと言っていたのを思い出し本書を再読したところ、見事に気分が回復した。私はいま、上機嫌だ。
主人公
山座次郎。32歳。六井信託社員。学生時代にはどうにかなりそうな気配もあったが、今は、まるっきりそんなものを持ち合わしていない。波風は真っ平ごめん。無理は一切しない。温室の中のメロンのように、丸く熟した世渡りをすることを唯一の念願にしている。
上記の山座がなんの間違いか二人の女傑に惚れられてしまう。一人は六井信託の専務のご令嬢で24歳の未婚の美女、名を貴子という。
褒め上手で、気が利いて察しがよくて、決して人の気を外さず、ほんのちょっぴり猥雑で、たいへん上手に他人の悪口をいう。生涯苦楽をともにして、共存共栄を計ろうというには、いささか物騒な性格なんだが、山座には、これが、なんともいえぬ魅力なのである。
山座は有頂天で、夢遊病者のように「貴子様、貴子様」と口走り会社でも馬鹿にされたりしているのだが、そんな山座の前にさらにもう一人の女性が現れる。
山座が、有楽町の省線ホームに突っ立っていると、草の茎のように細い脛をもった、目玉のキョロリとした娘が近寄ってきて、いきなりドスンと体当たりを喰らわせてから、「オイ、遊んでやろうか」と、いった。山座は、何の気もなく、「ウン」と、答えた。
彼女の名は礼奴(れいぬ)。父の仕事(毛皮の買い付け商)の関係で長くモンゴルの草原で包(パオ)を住居として暮らす。つまり育ちからして規格外で彼女の中には、果てしもない草原の起伏や、茫漠たる砂漠の向うに沈む大きな夕陽や、とかく大陸的なものがゆったりと展開している。
山座は貴子様と一刻もはやく結婚したいくらいだが、礼奴があらわれたあたりからどうも貴子さまの態度が冷たくなり始めたような気がする。礼奴には理屈はまったく通じず、気のないことを示してもこちらの意向はまったく受け入れない。
「ねえ、紳士さん、あたしにあんたの※※※※※※※※※」山座は、思わず、わッ、と叫んで、草の上に跳ね起きた。こんな厚かましい求愛の仕方ってあるものだろうか。一種兇暴な迫力があるばかりで、愛の感情などは露ほども感じられない。
どうやらこの礼奴が、山座のあずかり知らぬところで貴子様に逢いに行ったらしい。貴子さまからは「あたくし、ほんとうに、悲しいわ」というたった一行の手紙が寄越されてきた。その後は、山座が何度も訪ねても居留守を使われてしまう。
やけになった山座は礼奴とさんざん酔っぱらったあげく、ある生命の危機に陥る。奇跡的に生還し、すったもんだあったあげく、貴子様の別荘に乗り込み貴子様の浮気現に遭遇するのだが・・・・
とにかく、とにかく、とにかく楽しい。そして、人物の持つ魅力がすごすぎる。狂った調子の楽器どもが勝手気ままに演奏してるかのような、ジャジーな楽しさで溢れている。礼奴の突き抜け感がすさまじく、踊るように言葉を吐く。山座は感きわまると田舎弁丸出しで、貴子様は、「ほ・ほ・ほ・ほ」と笑うだけで、相手に「死ね」とテレパシーしてしまう。
軽妙洒脱で終始つらぬくかとおもわれる物語の終わり。思わず泣いてしまうくらいの切なさが胸を襲う。真実、光が差し込むような瞬間の訪れがある。結局、なにを書いても、なにを言ってもなんか違う気がする。最後に礼奴がさかだちするシーンを抜粋します。ここ、好きなんです。
礼奴は、両足の爪先をキチンと揃えて空へおっ立て、シンネリと逆立ちをしていた。襞の多い薄紗(ダンテール)のついた朱鷺色(ときいろ)の下着(シュメーズ)が、カトレヤの花びらのように優しく四方へ垂れさがり、その中心から、薄黄色の絹靴下につつまれた二本の足が、長い雄蕊(おしべ)のようにすんなりと伸び上っている。大きな蘭の花がひとつそこに咲き出したようにも見えたのである
感想『反絵、触れる、けだもののフラボン』福山知佐子著〜泥土の様な現象の海から、絵を、言葉を感応する。絵画写真映像批評エッセイストは絵を描くように文章を書く。

反絵、触れる、けだもののフラボン―見ることと絵画をめぐる断片
極度に詩的で哲学的なため、私にできるのは陶酔だけだ。
著者が鋭すぎる感性の持ち主のため、通常ABCDの順序で理解していくはずの世界の美しさや悲しさ、その他哲学的命題をABCをすっ飛ばしてDだけ感得して直観的に理解して書いてしまう。そのため、文章は論理的であるにもかかわらず、なかなか理解しがたい。感性の哲学、そして絵画論なのだ。
本書の著者、福山知佐子は画家であるが、本書のように絵画論も書けばエッセイ・批評も書く。亡き師毛利武彦との交感を記した文章は感動的だ。
誰かが死んだとき、そのとき、その人の眼の中の絵は、長い時間の記憶はどこへいくのだろう。誰かの眼の中の記憶を、誰かは想像しようとしていた。それは、そのひとが生きているときも、その人に触れられない現在もかわらない。
著者は「世界は絵よりも、より絵である。」と言う。「絵」は人間の側にではなく、世界の方にあるのではないかと。
絵のために私が世界をリストラクション(再構築)するのではなく、世界の予測不可能性によって、絶えず私がリストラクションされるのだ。
枯草の塊、しな垂れる茎の軌跡、苔、黴の模様、昆虫の足の動き、剥落、ずれ、不純物、白濁、薄闇、窪み、隈、錆びた杭、雨上がりの地面の斑、爆発、破裂、放棄、水蒸気、偶然の滴り、不揃い、混じる匂い、乱雑の奇跡、
ほんのわずかな獣じみた匂い、目を閉じて空中にたどる幽かなかすれの糸に引き戻され、私の『絵』が強烈に再来する。そのとき、「反絵」が『絵』となり「絵」が『反絵』となる。
著者の筆にかかると、故人だろうとなかろうと、とても同じ人間とは思えない。神にあらがう阿修羅のようで世界に対して命を刃に抜身の戦さを繰り広げている。彼女の眼は類いまれなく優れている。彼女にかかれば世界は絵となり、人はその最奥を隠すことは出来ない。
感想『青と緑』ヴァージニア・ウルフ著・西崎憲編・訳〜ヴァージニア・ウルフの入門書として最適。これはもうVRでは⁉️傑作『ボンド通りのダロウェイ夫人』。
『ボンド通りのダロウェイ夫人』
※引用はすべて本作より抜粋したものです。
この作品は傑作だ。正直タイトルはなんの面白みもない。なんの期待もしていなかった。内容もほとんどない。アラフィフのダロウェイ夫人がただ手袋を買いに行くだけの話。〈つまらない〉そうなるだろうと思っていた。
しかし読みすすめるうちに、戦慄しだす。人の意識がそのままにタレ流れている。終始いけないものを読まされている。おそろしく明け透けで、ある意味おそろしく誠実。このようなものを人に読ませようとする作家はあまり知らない。物を語ってない。人間のこころをただ見せられている。拒むことはできない。ナマの人間の思惑を、伺い知ることは通常できないからだ。こんなチャンスを逃すわけにはいかない。とても面白い。私はこの作品が大好きになっている。本家の『ダロウェイ夫人』も読まないと。絶対に。
やあ、素晴らしい朝だね
突然話しかけられる。
誰だ、おまえは。私はこれから手袋を買いに行くのだ、とダロウェイ夫人でありながら、読者でもある私は思う。
ロンドンを歩くのが好きなのよ
これまた突然、ダロウェイ夫人となっている私が言う。そうか。私はロンドンを歩くのがすきなのか、了解。と私は思う。もはや私とダロウェイ夫人は同じ意識を共有している・・・・。

人にはそれぞれ現実の世界とは別に、意識としての生活がある。それは絶対だ。いや、わかっている。もちろん現実のほうが絶対的だ。なんといっても腹はへるし、棒で叩かれれば痛い。身体にとっても心にとっても。打ちどころが悪ければあまつさえ血が流れるだろう。
しかしもし、人間に意識がなかったら(意識をこころと言い換えてもいいかもしれない)、外界の刺激に対して反射程度の反応しかしめさない単細胞生物のような存在だったなら、そもそもそこから『物語』は生まれないだろう。
そういう意味で、私たちにとって最も重視すべきは、日々めまぐるしく動く外の世界の事柄ではなくて、外の世界から刺激をうけて千変万化に変化する意識の世界なのではないだろうか。ウルフは個人の意識を、〈意識の流れ〉という手法で作品の中で表現し、それらを連綿と続く歴史や哲学などのようなもの、さらには圧倒的な圧力で人々の生活に押し寄せる戦争などといったものと同列の域までその威光を押し上げている。
小説を読み慣れている人ほど、ウルフの紡ぐ物語にはどこか違和感を覚えるだろう。通常の書き方で書かれていない気がする。これは人間の意識の特徴を使って小説を構築しているからにほかならない。意識は通常まとまりがない思考の連なりである場合が多い。視界から入る情報をもとに、耳から聞こえる音や会話をもとに、飛び石から飛び石へと次々とジャンプするように展開していく。それらの刺激をもとに形而上的に飛躍していくことだって多々あるだろう。
突然声をかけられたり、視界にはいったものから意識が展開していく様が『ボンド通りにダロウェイ夫人』ではうまく描かれている。自分と同じ過程で意識が展開していくこの物語を読みすすめていると不思議な事がおこる。
短編小説にもかかわらず、女性であるダロウェイ夫人と読み手である私が男性である性別の違いにもかかわらず、ダロウェイ夫人と私の年代の違いにもかかわらず、今まで私が読んできたどんな小説よりも、物語の世界への没入感がすごいのだ。これはもうVRである。
いままで経験したことのない現象に、ヴァージニア・ウルフが文学史に燦然と輝く巨人の一人であることを思い知らされる。ここまで実験的な小説を最後まできちんと読者によませ、あまつさえ感動までさせるというのは尋常ではない感覚と知性、技巧と勇気がなければ叶わないことだろう。
本書には他にも秀作は多数含まれているし、ヴァージニア・ウルフの人生、作品の特徴についても詳細に書かれている。難解で実験的な作風のものも多いが、どれも短編なので非常に読みやすく、こちらの集中力も続きやすい。入門書として最適ではないだろうか。実際私もヴァージニア・ウルフを読みすすめていこうと思っている。
本書によると、ヴァージニア・ウルフの人生には悲惨な出来事も多い。何より彼女は自らの命を自らで終わらせている。しかし本書で紹介されている彼女の作品たちには彼女が経験した幸せの輝きのようなものが随所にみてとれる。恋人たちのささやかで愛らしい仲むつまじさや、好ましい家族のぬくもり、そして戦争にさえ打ち勝つ意識の偉大さがみてとれる。彼女の不幸が、彼女の幸福がこの本にはたくさん詰まっている。当時におとらず激動の時代を生きている私たちにとって、そんな彼女の本を今あたらしく読むことができるのは、これもまたとんでもなく幸せなことの一つなのだろう。
感想『塚本邦雄』島内景二著〜『十二神将変』の復刊で話題の塚本邦雄。麻薬のような歌多数。錐・蠍・旱・雁・掏摸・檻・囮・森・橇・二人・鎖・百合・塵(左記短歌。読みは記事内にて)。
<少年時代、私は一通の手紙で彼と出会い、彼の「楽園」に案内されたのだった。塚本邦雄は、実際に逢うまでは実在の人物かどうか、私たち愛読者にさえ謎であった。〜本書より抜粋。
上記は塚本と15年の間友人とも師弟ともいえる関係にあった寺山修司の言葉。寺山はまた次のような言葉を残し、二人が組する前衛短歌の立ち位置を明確にしている。
短歌を始めてからの僕は、このジャンルを小市民の信仰的な日常のつぶやきから、もっと社会性を持つ文学表現にしたいと思い立った。作意の回復と様式の再認識が必要なのだ。〜本書より抜粋
与謝野晶子にしろ啄木にしろ短歌は歌人の人生から湧き出る泉とも血液ともいえる。歌人の傷口についた血で書かれたような短歌もあって、すべてが日常のつぶやきというわけではない。また、日常性があるからこそ普遍性を持ち合わせているのだが、確かに創造性の観点から考慮すれば、寺山のいうことも一理あるな、と思う。
さてさて、
タイトルの漢字の羅列。みなさんは読めましたでしょうか。私はさっぱり読めませんでした。実はこれも塚本邦雄の作品です。
漢字の読みは「きり・さそり・ひでり・かり・すり・おり・おとり・もり・そり・ふたり・くさり・ゆり・ちり」です。五・七・五・七・七のリズムに合わせて読んでみてください。短歌のリズムで心地良く読めることがわかるかと思います。
十三個の名詞がならべてあるだけなのに、頭の中に幻想的な物語が生まれてきます。先端の鋭さを感じさせる錐。毒を連想させる蠍。鋭さと毒性の末に人も死に、さらに旱(ひでり)が訪れて、貧困の末、雁(かり)を掏摸(すり)してつかまってしまう(檻)。深き森で橇(そり)にのって二人は逃げる。鎖につながれた二人は百合のようにはかない運命だ。塵のように散るだろう・・・。
塚本邦雄の短歌は難解なものが多く、個人的には少々レトリックが過ぎると感じるものもあります。ただ本書は、一首ごとに解説者の丁寧な説明が記載されています。これは非常にありがたく、塚本作品に触れるにあたって最良のきっかけとなり得ます。最後に印象に残った歌を4つ、本書よりご紹介します。ここまで読んでくださりありがとうございました。
燻製欄(くんせいらん)はるけき火事の香(か)にみちて母がわれ生みたることゆるす。
死に死に死に死にてをはりの明かるまむ青鱚(あおきす)の胎(はら)手のひらに透(す)く。
桐(きり)に藤(ふぢ)いづれむらさきふかければきみに逢ふ日の狩衣(かりぎぬ)は白。
掌(てのひら)の釘の孔(あな)もてみづからをイエスは支ふ風の雁來紅(かまつか)。
これで貴方もジュウラニアン。作家たちがこぞって絶賛する久生十蘭とは一体何ものなのか。変幻自在〈小説の魔術師〉久生十蘭のおすすめ短編小説11選。
その百科全書的知識、博覧強記の作風で〈小説の魔術師〉とまで言われた作家が、かつて日本にいました。久生十蘭という名前の作家です。
年季の入った読書家や作家の間に熱狂的なファンが多く、そんな彼らは〈ジュウラニアン〉と呼ばれています。
そんな久生十蘭の魅力あふれる作品を、ジュウラニアンを自称する私の視点からランキング形式でご紹介。膨大な作品の中から本当にすばらしいものだけを記載していきます。たまたまハズレをひいて、読まなくなるのはもったいなさすぎる!その思いからこの記事を書かせていただきます。よろしくお願いいたします。

目次
1.久生十蘭とは。
「この人はなんでこんなにも色んなことを知っているのだろう」と、その博学多識ぶりに驚きもしたが、そんなことに一々驚いていると興を殺がれるので、やがてなんとも思わなくなってしまった。〜中略〜久生十蘭の前で「驚く」ということをしても無駄である。そんなことをする前に、おとなしく受け入れてしまった方が、ずっと得になる。〜橋本治『定本久生十蘭全集月報1』より。
経歴
本名は阿部正雄。1902年(明治35年)に北海道函館市にて生まれます。回漕業を営む祖父に養育されました。15歳のころ学内で事件を起こして、函館中学校を中退しています。17歳で編入学した、東京の聖学院中学校も退学しています。18歳で函館中学の先輩の父が経営する、函館新聞社に入社し記者となっています。
20歳、函館のアマチュア演劇グループ「素劇会」の結成に参加。このころギターやマンドリンなどもよく弾いている。21歳、文学グループ「函館文芸生社」の同人となる。22歳〜26歳、同人誌に詩を発表、素劇会にて役者として活動、また函館をさる決意をし東京の岸田國士のもとにおもむき、彼の編集する演劇雑誌『悲劇喜劇』の編集に携わる。
27歳、戯曲を発表。劇団の旗揚げ公演で、演出助手なども経験。11月になると、シベリア鉄道経由でパリへ向かいます。28歳(昭和5年)フランス滞在中の詳細は不明で、国立工芸大学でレンズ工学を2年、他校で演劇を2年学んだとされ、夏休みには各地を旅したとされています。
パリの日本人の中では画家の青山義雄を頼りにし、佐伯祐三の姪、杉邨ていは恋人的存在であったと言われています。パリの十蘭のもとに母親の鑑が身をよせ、華道の挿花展を開くこともありました。母親の帰国後、一時神経衰弱ぎみになり、青山の世話で地中海沿岸のクロ・ド・カーニュにて転地療養をします。快癒に向かうとともに、モンテカルロのカジノに通い、また南フランス各地を旅しています。
31歳(昭和8年)日本に帰国し、雑誌『新青年』にトリスタン・ベナールのコントを翻訳。同誌に発表。32歳、同誌に『ノンシヤラン道中記』を連載開始。日本での執筆活動を本格化とともに舞台監督なども務めます。以降掲載誌の幅をひろげ、精力的に作品を発表しつづけますが、41歳(昭和18年)海軍報道班員としてスラバヤ、ニューギニアなど南方へ派遣されます。42歳、南方より無事帰国。帰国後も精力的に作品を発表する。45歳のとき、鎌倉材木座に転居。46歳、同じ鎌倉材木座でふたたび転居。50歳、『鈴木主水』で第26回直木賞を受賞。53歳、『母子像』が『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙主催の第二回世界短編小説コンクールにて第一席となる。55歳6月食道がんで入院。10月自宅にて死去。
※上記経歴は講談社文芸文庫『湖畔・ハムレット』文末の年譜を参考にしています。
2・久生十蘭のおすすめ短編小説10選。
『黒い手帳』

自分の机の上にいま一冊の手帳が載っている。一輪挿しの水仙がそのうえに影を落としている。一見、変哲もない古手帳にすぎぬが、この中には、ある男の不敵な研究の全過程が書きつけられてある。それはほとんど象徴的ともいえるほどの富を彼にもたらすはずであった。その男は一昨日舗石を血に染めて窮迫と孤独のうちに彼の生を終えた。
パリで10年、ルーレットの公式を解き明かそうと研究に明け暮れる日本人の男と、彼をとりまくアパートメントの住民が巻き起こす事件が描かれます。
もうこれ以上ないほどの完成度の高さです。私はもう10回以上読んでいますが、毎回新鮮な驚きと感動を呼び起こされます。何度も読める作品と出会えることは、私たち本を読む人の最高級の幸せではないでしょうか。
久生十蘭はその多くの作品を雑誌『新青年』に寄稿しています。本作も同様で、雑誌の掲載する作品の特徴からか、一見ミステリー仕立ての構成となっています。
しかし、単に謎を解明するというよりは、根本的にもっと深い部分を描いています。特に『黒い手帳』はそのお手本のような作品です。人間の欲望、純粋さ、友情、愛などについて冷静な筆致と極度に削ぎ落とされた言葉で表現されています。私はこの作品を手放しで絶賛します。読まなければ、ある程度の意味で(もちろん人によって程度はことなりますが)人生を損すると思います。本当に、本当に、オススメです。
『湖畔』
初出から15年かけて改稿された、伝説的な作品。『湖畔』を読めば、久生十蘭が他のどの作家とも似ていないことが確実にわかる。

この夏、拠処(よんどころ)ない事情があって、箱根芦ノ湖畔三ツ石の別荘で貴様の母を手にかけ、即日、東京検事局に自訴して出た。
私が始めて読んだ久生十蘭作品がこの『湖畔』です。一気に魂を持って行かれました。自己顕示欲が強く、卑屈で利己的な男が主人公で、2歳にもならない息子に手紙で自分の失踪の真相を語り聞かせていきます。
久生十蘭の描く登場人物は、男性だろうが女性だろうが関係なく、非常にエネルギッシュで、図太く、生き様に凄みがあります。善悪というしばりを超越したようなキャラクターも多く、現代に生きるわたし達からみてもその奔放さに驚きを感じます。
完璧主義の十蘭の改稿癖は有名で、本作は初出から15年後に大幅に改稿されたものが出ています。ノワール小説かと思いきや純愛小説!?先の読めない物語展開と、引用した冒頭の一文から終幕の一文まで、一分の隙きもない完成された物語世界が堪能できます。
『定本久生十蘭全集・別巻』の帯で、小説家の三浦しをんさんが推薦文で『湖畔』について以下のように述べています↓
はじめて読んだ久生十蘭の作品は『湖畔』だ。あるアンソロジーに収録されていたのだが、端整かつ異様な迫力を宿した文章といい、ほのかな官能の香りといい、ひときわ輝く暗黒の星のような小説だった。アンソロジーのなかで、『湖畔』だけを折に触れて何度も読み返さずにはいられなかった。〜三浦しをん『定本久生十蘭・別巻』より抜粋。
※改稿前と後の比較などは『定本久生十蘭全集1』国書刊行会の解題の項で非常に詳しくかかれています。
『母子像』
GHQ占領下の日本に住む少年の物語。

頭が良く、善良だったはずの少年が、いくつもの奇行をして警察に捕まっているところから物語は始まる。無関係のものから見ると奇行にみえる数々の行動も、少年からするとそれぞれ目的を達成するために、理知的に行ったもの。少年の心の声によって私達はそれを知ることができる。理想と現実とのギャップを埋めるために、行動を続けた少年だが、その差が行動によって埋められなくなると、そこに待っているのは果たして・・・。
吉田健一訳による『母子像』は、1955年(昭和30年)に『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙主催の世界短編小説コンクールに参加して第一位を獲得している。(※)
※ 占領するものと占領される者との親密な関係は、長らくメディア検閲の対象でした。『母子像』の出版と受賞は、検閲が終了するタイミングと重なるため色々と憶測もあるらしいですが、それを全く抜きにしても本編は非常な名作であることを自信をもってオススメします。
『春の山』

八月にレジェが死んだと思ったら、この月の六月にユトリロが死んだ。パリでは毎日のように人生の一大事に逢着している。そちらはどうだ。古沼の淀みのなかで、相も変わらずフワリフワリしているのだろう、などと生意気なことが書いてある。ユトリロが死んだことが、はたして人生の一大事かどうか、よく考えてみないとわからないが、周平の住んでいる世界はあまりにも無事で、ちょっと気をゆるめると、つづけざまに欠伸がでてとまらなくなる。〜本編より抜粋。
蘆田周平は、親戚の売り空家の管理人。画家の卵でもあり、15間もある広々としたその空き家で、好き放題に絵を書いて過ごしている。サンルームでぼんやり絵を描いていたら、まわりの景色がいつの間にか春になっていた。そんなある日、周平の周囲の人間が、やたらと周平に屋敷を留守にするようあれやこれやと誘いにくる。なにか企みがあるらしい・・・。
冒頭で、友人にもらった手紙の中の【一大事】という言葉がキーワードとなっている。周平のあまりにも平和な日常と後半のその対比がとても良くできた作品だ。
『カストリ候実録』

SF以外ならば、ほとんどのジャンルを書いているであろう久生十蘭だが、本編は歴史サスペンスの傑作だ。もともと十蘭には歴史ものの傑作が多い。とりわけ凄惨な史実を題材としたものには強烈なものが多く、『美国横断鉄道』や『雪原敗走記』などは一度読んだら二度と忘れられない凄みがある。インターネットもない時代に、これほどまでにニッチな部分に目をつけて、徹底的に調べ尽くした上で作品を書き上げたことに驚嘆を覚えずにはいられない。他作品にも見られる完璧主義的傾向と博覧強記の知識を支える異常なまでの好奇心が、史実をもととした小説の構築と相性が良いのだろう。
あらすじ
時は1792年フランス革命。ギロチンで処刑されたルイ十六世の嗣子わずか8歳のシャルル(ルイ17世)は母からも姉からも引き離され、廃塔のてっぺんに幽閉され虐待を受ける。1795年6月8日ついに消耗し尽くしたシャルルは幽閉されたまま死んでしまう。
ルイ17世がタンプルで死んだといわれた年から数えて三十三年目の1828年の4月、ルイ17世なりと名乗るアンリ・ルイ・ヴィクトワール・リシュモンという男が膨大な書類入れを携えて巴里にあらわれ、ノルマンディ及びナヴァール王領地の所有者たることを認知してほしいという請願状をフランス政府に提出した。〜本編より抜粋
それまでにも幾人もいた自称ルイ17世たちとは異なり、リシュモンは書類や所持品などは指摘するほどもないほど完璧。また、彼が生存した裏工作なども理路整然と説明するのであった。彼が本物かと大勢が決し始めたとき、さらにもうひとりルイ17世を名乗りでる男が現れた・・・・・・・。
歴史ミステリーとして最高に面白い作品ではありましたが、現実には2004年にDNA鑑定の結果で、幽閉中に亡くなったのがルイ17世本人であることが証明されました。十蘭自身この悲しい結果を知る由はありませんでしたが、それだからこそ生まれた傑作短編です。
『レカミエー夫人〜或いは、女の職業』

本編は大衆小説として書かれました。重々しい歴史ものとはうってかわって、非常に読みやすく、コミカルな作品です。どこか夢見勝ちな4名の女性が、自分たちは4人で一人前だと(ボーット倶楽部)なる集まりを定期的にひらき、近況を話し合います。そこに一人の美青年が現れ・・・・みたいな話です。乙女チックとも漫画的ともいえるような雰囲気ですが、書いているのが久生十蘭なので初めて聞くような言い回しや、単語がたくさん出てきます。同じ日本人のはずなのに、時代と知性が異なると、ここまで書くものが異なるものかと不思議に感じます。軽い作風がお好きな方にはぜひオススメしたい作品です。
『奥の海』

あらすじ
天保7年の大飢饉がつづく中、京都所司代に務める貧乏侍の金十郎は、嫁(ちか)を迎えます。ちかの実家は位こそ公卿でしたが、立派なのは館だけで実は貧乏。飢饉のおりは、水で腹をふくらましたり、庭で蛇をつかまえて食べたりしていました。
晴れて金十郎の館へ来たちかは、夕餉のさい「白飯をこんなにもいただけるのでしょうか」といって涙ぐみ、食うわ食うわ気持ちの良いほど白飯を食べまくり、「足るほどに頂戴しました」といってニッコリと笑ったのです。
金十郎はこのちかの笑顔が心にささり、家財を潰してまで食費にあてますが飢饉による物資の不足はすさまじく、だんだんと食えなくなっていきます。そんな折、ちかが突然姿を消します。机の上に金子を残して。金十郎はちかへの気持ちが愛だったことに気づき、職を辞し命がけの捜索の旅に出ます・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まったく久生十蘭という作家は本当に変幻自在というか神出鬼没というか、世界中のどんな場所でもどんな時代でも現れて、とんでもないクオリティの作品をポコっと生み出してしまいます。
すべての作品がすべらからく洗練されたもので、どちらかというと、どの時代の風俗を描いた小説でも、すべて現実と類似したパラレルワールドの中のように登場人物たちが振る舞います。それはどこかコミカルであって、反面命がけのシリアスだったりもします。
私も久生十蘭の作品を長年読んでいますが、この人は本当に明治生まれの日本人なのだろうか。どちらかといえば、異星から来て人の皮を被って小説家として擬態しているといわれた方がよっぽど納得がいくと今だに思っています。
『幸福物語』

あらすじ
空襲で焼け出された主人公(黒田光太郎)が古借家に越してくるところから話は始まる。隣家の大屋敷からは戦時中にそぐわぬのんびりとしたテニスの音や、ピアノの音が聞こえてくる。ある日、避難警報をまつ光太郎が、鉄兜をかぶって縁側にいると、テニスボールが敷地内に飛んできて光太郎の頭にぶつかった。ボールを打った主は隣家の女主人で、若く美しいもののどうやら頭がおかしいようだった・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
空襲という命の危機と、常識からはずれてはいるが純粋な愛の物語が同時に展開されている。コミカルな読み味でありつつ、物語がおおきくうねる感じも、読んでいて感心させられる。本編は読後感がよく、ハッピーエンドがお好きな方にはおすすめできる良作だ。
『大竜巻』

正直なんのジャンルだかよく判らない。いやそうではない、なんだかよく判らなくなるほどにめっちゃ面白いのだ。タイトル通り、大竜巻に飲み込まれる話なのだがそこそこ短い文量のなかにドキドキハラハラがこれでもかと詰め込まれている印象だ。
ストーリー展開も怒涛なのだけれど、それぞれのキャラクターも立っていて読み応えがある。POPに読み進めることもできれば、一気に深淵に引きずり込まれそうにもなるエッジの効いた小品といえる。
『ノンシヤラン道中記』

短編〜中編ほどの文量があり、とてもコミカルな作品。活弁士が面白おかしく話しているような文体で、パリに留学している若者二人が、各地を旅する様子が描かれている。狸にどことなく似ているタヌ子と、キツネにどことなく似ているコン吉の珍道中。読み始めこそ、いままで読んだことのない文体に違和感を覚えるものの、読み勧めていくうちにそれが段々と癖になっていく。タヌの破天荒な思いつきにコン吉がしいたげられる展開が基本姿勢であり、なぜかコン吉にシンパシーを感じてしまったそこの貴方はもうこの話は絶対に読まなくてはなりません。これはサダメなのです。抱腹絶倒。とにかく面白いです。私も何度も繰り返し読んでいます。
『心理の谷』
あらすじ
しがない会社員の山座(やまざ)は、どういうわけか社長令嬢の貴子様から好かれている。山座は軽薄な男で、貴子様と結婚することだけを夢みているのだが、そこに礼奴(れいぬ)というモンゴルから来た娘に好かれてしまい、七転八倒の物語が開幕する・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
終始ご機嫌なドタバタラブコメディなんだけれど、山座の持つ高所恐怖症が物語にトリッキーな要素を加えている。久生十蘭の恋愛ものの作品の中では、POPさではおそらくNo.1なのではないかと思うほど明るく、楽しい作品だ。
バラエティーに富む物語に共通しているのは、いずれの人物も生と死の際にある、ということ。その際のポジションの取り方が、非常にユニークなのである。対極にあるはずの二つの世界を、しれっと越えるので。ぼんやり読んでいると、たった一行でガラリと違う状況に変わっていることがあり、軽やかな文体であっても油断はできない。読む側にも快い緊張感をもたらしてくれる。小説の醍醐味ってこれですよ、と初めて読むのになぜか懐かしい気持ちになったのだ。〜東直子・理知と茶目と消失『十蘭万華鏡』河出文庫より抜粋。
事物は移ろい消えてゆく。砂漠の英雄も、戦前の軽井沢も、草原の娘も、真珠貝成金も、馬鹿囃子も、どこかへ行ってしまった。しかし言葉さえあれば、それらを呼び戻すことができる。十蘭を読んで思うのはそこだ。繁栄してほとばしる言葉、細部を穿つ描写、愉しげなレトリック、しゃれたルビ・・・・ひと言でいえば巧いということなのだが、その巧さのおかげで、私たちは本を開けばいつだって、かつての豊穣で猥雑な世界と固く抱き合えるのである。〜阿部日奈子(詩人)・『十蘭レトリカ』河出文庫。解説より引用。
そういえば、十蘭の作品も、緻密な技工をこれでもかというほど凝らした人工物でありながら、西洋と東洋、現在と過去を視野に収めた、広い世界観を持っている。その意味で、いかにも「パノラマ」的と言えるのではないだろうか。自在な語りに引き込まれ、細道を先へ先へと進んでいくと、いきなり呆然とした空間に放り出され、そこで小説はあっけなく終わってしまう。途方に暮れてきょろきょろ辺りを見回す私たち読者の姿を、パノラマ館の仕掛け人たる十蘭は、隠れて遠いところから眺めているに違いない。内心「してやったり」とほくそ笑みながら、しかし、あいも変わらず真顔のままで。〜石川美南(歌人)・『パノラマニア十蘭』河出文庫解説より抜粋。
精密に積み重ねられていく十蘭の文章は、理知的で湿っぽさが全くない。心理は詳細に追っているが、情景描写と区別しない形で客観的に描かれ、余計な感情の言葉が入り込むことはない。しかし、最後になって、クる。津波のように、人生のやるせなさやどうすることもできない切なさが、短編の終わりにふりかかってくるのである。〜東直子・『十蘭万華鏡』解説より。
事実から傑作小説を生み出す技を言葉の錬金術というなら、十蘭は間違いなく稀代の錬金術師だ。しかしその術は、デモーニッシュな霊感の産物ではなく、「爆風」に見える冷静な精神に拠っている。常識人の透徹した眼、それこそがいつの世にも得がたい賢者の石なのである。〜阿部日奈子(詩人)・『十蘭錬金術』河出文庫解説より抜粋。
フィクションとしての小説というものが、無から有を生ぜしめる一種の手品だとすれば、まさに久生十蘭の短編こそ、それだという気がする。作者は作品のかげに完全に隠れてしまって、ついに最後まで、ちらりとも姿を現さず、私たちの目をうばうのは、凝りに凝った、あまりにも凝りに凝った作者の小説技巧のみなのだ。〜澁澤龍彦『久生十蘭ジュラネスク』より抜粋。
4・まとめ。
長らく読んでいただきありがとうございました。久生十蘭に対する情熱だけでこの記事を書いていますので、お目通しいただきとても嬉しいです。久生十蘭が生前住んでいた鎌倉材木座の番地付近を、ニヤニヤしながらウロウロと歩き回るような私ですがこの記事が少しでも久生十蘭を知っていただけるきっかけとなったのならば幸いです。まだ未読の方はぜひご一読ください。ぶっ飛ぶような読書体験が必ず得られます。断言いたします。既読の方はこれを機に再読していただけたら嬉しいです。もっと知られていい作家だと思いますよね。ありがとうございました。
他、偏愛作家オススメ記事はこちら↓
感想『粋に暮らす言葉』杉浦日向子著〜かわいくもかわいそうな私たちよ。くだらないからおもしろおかしい生をありがとう。
杉浦日向子(すぎうら・ひなこ)
1958年11月30日、東京生まれ。1980年「ガロ」で漫画家としてデビュ―。江戸の風俗を生き生きと描くことに定評がある。1993年、漫画家引退を宣言。「隠居生活」をスタート。江戸風俗研究家として多くの作品を残す。2005年7月22日、下喉頭癌のため46歳で逝去。
杉浦日向子、生前の言葉集。彼女のリズム、江戸っ子の息遣いに溢れている。
面白うてやがて悲しき鵜飼かな
芭蕉のこの句を思い出すたび、私の中に江戸が浮かび上がる。華やかで、悲しい。馬鹿馬鹿しいけど愛おしいのだ。
ざっくり言うと江戸は、武家の町(山の手)と庶民の町(下町)に分けられ、本書は主に、庶民(下町)の文化を対象としている。
当時の江戸は人口的に見て、世界最大級の都市であり、成人男性の識字率(文字が読めること)も70%を超えている(同時期のロンドンは20%台)。狭い一間に二世代が同居するのも当たり前で、人口密度は現代よりもはるかに高い。
江戸は女性が少なく、武家をのぞく江戸っ子の8割は生涯未婚で過ごした。15歳以上の成人男性の平均寿命は、確か60歳台だったかと思う。幼児も含めてしまうと30歳台まで数値はさがる。 週に数日、日雇いで働けば食べていけたらしく、「宵越しの銭は持たない」とは案外リアルな生活感から生まれた言葉らしい。
江戸気質は上記のような諸条件から生まれたものである。
著者は以下のように言う。
江戸の遊びはいつだって、喜怒哀楽の場数を踏んだ、大人たちが主役である。
なるほど。人生60年。独り身ばっかりのその日暮らしの社会では、太く短く風流に生きようとするのは、むしろ自然な成り行きのように思える。晩年が60代であれば、体力も気力もまだ余力はあるだろう。
頭が禿げる。白髪になる。江戸っ子はこれを風格がついたと喜ぶ。若さにしがみついたりはしない。若者は「若造」「青二才」などと馬鹿にされ、むしろ渋みをつけようと老けて見せたりもする。著者はまた、こんな風にも言う。
江戸っ子の基本は三無い。持たない、出世しない、悩まない。
江戸では諦観(ていかん)の文化が発達していて、あきらめることで楽しみが広がるとしている。あきらめない内はまだ子供だとみなす。これはむしろ、積極的にマイナスを肯定する意味合いが強い。価値転倒に近い感じかなあ。
落語家・立川談志の言葉を思い出す。
「人間は寝ちゃいけない状況でも、眠きゃ、寝る。酒を飲んじゃいけないと、わかっていてつい飲んじゃう。夏休みの宿題は計画的にやった方があとで楽だとわかっていても、そうは行かない。八月末になって家族中が慌てだす。それを認めてやるのが落語だ。寄席にいる周りの大人をよく見てみろ。昼間からこんなところで油を売ってるなんてロクなもんじゃねェヨ。でもな努力して皆偉くなるんなら誰も苦労はしない。努力したけど偉くならないから寄席に来てるんだ。『落語とは人間の業の肯定である。』よく覚えときな。」〜『赤めだか』立川談春著より抜粋
江戸も同じだ。現代よりも、はるかに個人の可能性の幅が狭かった時代、風流を解する美意識と、あきらめを受け入れる枯れの美学を持つ江っ子の生き方は現代に求められる生き方だと思うのだ。 それはまるで嘘みたいな青空とカンカンに照りつける太陽と、心地よい春風のあの江戸である。今日もまた江戸っ子の馬鹿みたいな怒鳴り声がこだまする。
悩んでるって?
哲学?宗教?いや、江戸だよ!!
杉浦日向子に言われた気がする。そんな本でした。
感想『夜の果てへの旅 下』セリーヌ著〜エリ、エリ、レマ、サバクタニ!素晴らしきこの世界を怪物セリーヌと共にこき下ろす。

『夜の果てへの旅』は「明確な目的のある本」であって、その目的とは現代の人生の-いや、むしろ人生そのものの恐ろしさ、意味のなさに対して抗議することである。
上記はジョージ・オーウェルの評論『鯨の腹の中で』からの引用で、ある意味ではその通りであるが、この一文だけ読むと多少誤解を受けやすい。『夜の果てへの旅』を言葉でまとめようとすると、上記の引用文は非常に的を得ている。本書は世界への呪詛で満たされているからだ。
下巻ではバルダミュは苦学の末、医師免許を取得。放浪癖はなりを潜め、スラム街のようなところで場末の開業医として安住を目指している。医者としてのバルダミュは、善人になりきれない悪人のような雰囲気で、気が弱いために患者から謝礼金を取れない。無償で治療することもしょっちゅうなのに、何故か患者からは疎まれている。
以降果てることなく人生への、つまり仕事への、女への、男への、世間への、貧乏への、二四時間への、考えうるありとあらゆるものへの愚痴、諦念、冒涜が繰り返される。そこには向上心は欠片もない。あるのはただ現状から抜け出したい、少しでも楽に暮らしたいという切実な願いだけである。地獄のような戦争体験、熱帯での廃人、臨死体験を嘗め尽くしたバルダミュは、下巻ではおそらく少し壊れている。冒険心は影をひそめ、活力も感じられない。
私個人の感想としては上巻の終わり方が素晴らしくそこで終わっていた方が良かったような気もする。上巻で、果敢に世界に悪態をついていたバルダミュはすでに変わってしまった。彼は敗れたのだ。徹底的に。そういう意味で、冒頭の引用文は正しい。異なるのは呪詛が結果として読者の心情を代弁していることにある。
誤解を恐れず言えば、バルダミュはゴルゴダの丘で「エリ、エリ、レマ、サバクタニ(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)。」と叫んだあの男のようにも思える。果てしない夜の旅は、世界に対する呪詛の旅は、バルダミュがすでに終えた。私達の苦しみはいつでも彼にわかられているし、その悲しみはいつでも彼と二等分なのだ。