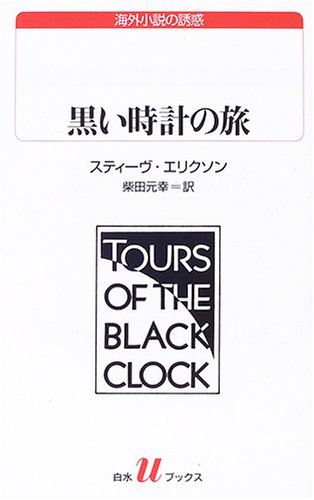感想『或る少女の死まで〜他二篇』室生犀星著〜痕跡本のつなぐもの。リアルタイムにタイムリープする室生犀星と私と或る少女。

古本に、前の持ち主の書き込みのある本を、痕跡(こんせき)本というらしい。
店頭の100円均一で買ったこの本にも読後、巻末に書き込みのあることに気づいた。
-------------------------------------------------------------

79 3/22 ← はとと西武にいった日
素直で きれいな 小説だ。 読みやすくて 教科書に
でも取られそうだな.とか思ってたら ユリちゃん
が.モギテストでみたことあるって言ってた。
或る少女の死まではちょっと たいまんしてよん
だけどもっとしっかり読んだら いろいろ 意味
あるのかも。 幼年時代は ほんとに 透明で
少年がシロに言う 「負けたら帰ってくるな」って
言ったのが印象的。
正義感の強い少年。3作目まで それがつらぬかれてるみたい。
--------------------------------------------------------------
普通読書って、リアルタイムで感動を人と分かち合えないもんだけど、この時ばかりはびっくりした。本文読み終わって、解説読んで、余韻にひたりながらペラペラページをめくっていたら、上の可愛らしい文章が何年発行、何版なんて書いてあるページの上に書いてあったのだ。
79って記載は、多分1979年ってことだと思う私が生まれる前に、多分10代であった少女と時空をこえて、一緒にお茶でも飲みながら感想を言い合っているイメージが浮かんのだ。この時はほんと、読書っていいなあ~、と感じたものだ。
肝心の本の内容の話だけど、上の可愛らしい感想文の通りで、透明感のある、とっても綺麗な、凛とした印象のある物語だった。著者である室生犀星(むろうさいせい)の自伝的な作品と言えるだろう。
個人的には、犀星の文章の透明感、美しさの秘密は「劣等感」にあると思う。犀星はある意味、両親から捨てられた経験を持っているのだが、そこから派生する悲しみや、寂しさ、姉や義父との交流を非常に美しいものとして捉え、告白し書いています。
作家っていうのは、いかに芸術的に高いものを生み出せるかと言うよりも、弱みを正直に告白できる人なのだと、犀星から教わった。
それだけに、文中にある、彼の友人との付き合い方は心にせまるものがある。
「やはり苦しいかい」
彼らはお互いを気にかけあい、食べてなければ一枚きりの着物を友のため金に替え、喧嘩してれば助太刀し、警察につかまれば、奴はやっていないと、全力で弁護しました。これらを遠慮がちに、照れながら行うところに犀星の良さがあります。
室生犀星は本当に油断のならない作家です。綺麗な文章だと思って読んでいると、突然ぞっとするほど野生的な印象を受けることがあります。
やさしくて、繊細で、ガラスのように透明で、なおかつ鋭利でもある。『香炉を盗む』や王朝ものなどを読んでみても、室生犀星の幅の広さ、懐の深さを感じることができます。
感想『極北』ポール・セロー著〜終末文学の傑作。終わりつつある世界の中で人は残されたわずかばかりの食料を、快楽を、権力を奪いあう。そこに道徳が介入できる余地はわずかだ。だがその僅かな閉所こそが、善性であり、人間性というものだ。
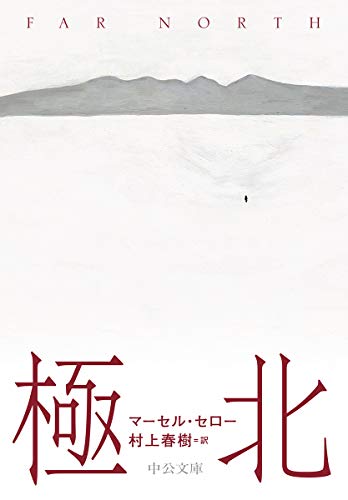
ポール・セロー著『極北』。
無人の店、窓ガラスはすべて割れている。ビルはもぬけの殻。手入れもされず、そもそも誰いなくなって長い。世界的に都市は廃墟となっており、おそらく電気や水道などのインフラは通っていない。道路は荒れ、人はほとんど住んでいない。そんな死滅状態になって、おそらく数十年が経っている。
主人公はメイクピースという風変わりな名前をしている。平和主義の父親がつけた名らしいが、どうやら本人は気に入っていないらしい。この終わりかけた世界のある都市で、そこの廃墟に居を構えている。名前のわりに生きるためには闘いを厭わないタフなやつだ。おそらく他に近隣一帯に住んでいるものはいないと思われる。まず食料が少ない。他にだれもいないから自分で猟をするか、廃墟から食料を探すしかない。
メイクピースは世界が壊れ始めたとき、警察官として働いてた。街の秩序を守ろうとしてきたが、ある時から信じられないほど惨めな様子をした人々が大量に街に入り込んできた。守るべき人たちが沢山いた 。だが、少ない資源を暴力によって奪おうといてくる輩もいた。治安は極度に悪化した。
そして今は誰もいない。人をほとんど見かけることがない。世界は確実に死にかけている。そんなとき、窓から人が落ちてきた。人と人とが出逢えば即殺し合いにつながるせおの状況の中で、メイクピースは彼を撃ってしまう。だが彼が年端もいかない少年だったことに後悔を感じ、彼を看病し、一緒に住むようになる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんの期待もせずに読んだら傑作だったという嬉しい誤算を味わえた。世界の終わりの中で生きるために抗う物語は、ただそれだけでも読んでいて楽しいものだが、本書には読者の予想を裏切るさまざまな工夫が施されている。
読んでいて辛い部分も沢山ある。この世界では人の命は非常に軽い。命は弱いし、失われやすいからだ。相対的に資源や食料は非常に貴重だ。当然奪い合いが起こる。人は生きるために殺しあう。残念なことに豊かな世界でないと人々は助け合えない。この世界の人々におそらく起死回生の一手はなさそうだ。おそらくそう遠くない未来、人類は滅ぶだろう。そんな世界に生きていく上で、私たちは一体どう生きるべきだろうか。もちろんそんなことはわからない。わかっているのはこの本を読んで良かったという自分の気持だけだ。
感想『コーヒーもう一杯』山川直人著〜あなたのそばで何があっても寄り添ってくれるものそれはそうコオヒイ。
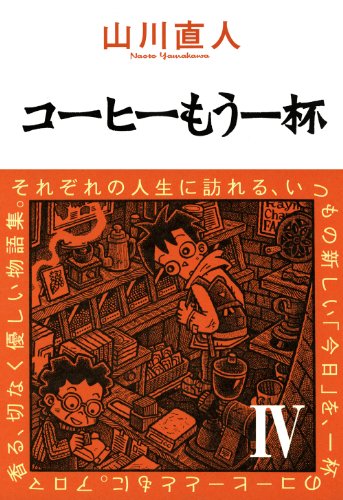
コーヒーが好きだ。
好きがこうじてカフェで6年ほど勤めていたことがある。そう言うと人は、豆やら淹れ方についてあれこれと聞いてくるのだが、実はよく知らない。 私は舌が馬鹿なので、インスタントのコーヒーの方が豆から挽いたものより美味しく感じる。ミルクと砂糖もガブガブ入れる。沸騰させると湯の成分が壊れるらしいが、猫舌のくせに鍋でグラグラ沸かした硬いお湯で淹れるコーヒーばかり飲んでいる。電気ポットで適温に調整されているお湯なぞ、心に響かない。
さらに言えば、ああ、あの店のあの不味いのが無性に飲みたい・・・。なんて時もあったりする。振り返って見ればコーヒーなるものは不思議な飲み物で、私の思い出にはどの場面にも意識無意識にかかわらずコーヒーの存在があった。サヨナラばかりの人生でコーヒーはいつでもそこにあったし、これからもあるだろう。
そんなことを私に考えさせるきっかけとなったのが山川直人のコミック「コーヒーもういっぱい」だ。何とも言えない嘘のような素晴らしさで、正直何を書けば良さが伝わるのかさっぱりわからない。太い線と広い面で細かく描写された絵は畦地梅太郎の木版画のようで、吹雪の戸外から暖房の効いた部屋に帰ったかのような暖かさを感じさせる。心がポカポカし思わずホッと息を吐いてしまう。
短編であるが毎話ストーリーが素晴らしい。ノスタルジーと哀切に満ちた人間ドラマで登場人物の全てに深い味わいを感じさせる。共感性にあふれ独創性も申し分ない。印象に残ったのは3編。あらすじの説明はしてもあまり意味がない。本書の魅力の源泉は多分そこにはないからだ。
ただ、どれも素晴らしい。
記憶のそこの澄んだもの。
何度も何度も読み返した。
万物は流転するのだから、税率が上がるだの、年を取るのは当たり前だの、紛争が絶えないだの、論文を捏造しただの、3時間前の俺は一体どこに行ったのだろう?だの全ての変化や疑問も当然なのかもしれない。
でも本書は教えてくれる。悲しみだって苦いばかりではない。コーヒーのように香るってことを。大切なものは今も昔も変わらないってことを。変わらないものに目を向けよう。さあ、「コーヒー、もういっぱい。」
感想『わたしがいどんだ戦い1939』キンバリー・ブルベイカーブラッドリー著〜障害を持つ少女が、虐待や戦争に健気にも戦いを挑む。勇気という武器。ありったけそして唯一のもので。
1939年、第二次世界大戦のさなか。ロンドンに住む十歳の少女エイダは、母親から虐待を受けている。右足に障害を持って生まれ、彼女を人目にさらしたくない母親はエイダを監禁し、ことあるごとに暴力をふるう。そのためエイダは心に傷を負っているし、外の世界のことを何も知らない。<草>とか<木>とかそういったものも判らない。
彼女にはジェイミーという弟がいる。六歳。ジェイミーは健常者のため、外には出してもらえる。だがエイダと同様に暴力は振るわれている。十分な食事も与えらえていない。そのため外で盗みを働いている。
ある日エイダは、ジェイミーの通う学校で集団疎開があることを知る。ロンドンの爆撃が不安視されているからだ。そして母親はジェイミーだけを田舎にやろうとしている。<お前のみっともない足は誰も見たくないんだよ。>エイダは母の目を盗んで弟と一緒に疎開する決心をする。歩く練習を始める・・・。
本当に、幼い子供がひどい目にあっている物語は読んでいて辛いものがある。ひどい目に合わせている張本人が親である場合はなおのことだ。愛情を、自己を肯定する力を子供が持つためには何より親からの無条件の愛情が必要であるはずなのに。
幸いエイダとジェイミーは疎開先でスーザンという素晴らしい女性と生活を共にすることになる。親から愛情を示されたことのないエイダは、スーザンの親切さや優しさが理解できない。信じてはいけないような気がしている。そのため何かと憎まれ口をたたいたり、反抗したりする。
浅はかな私は<せっかく助けてもらってるのに何だその態度は>とちょっとカチンときたりもした。それは多分私が親の立場だからだ。私が仮に今10歳だったら、今まで与えられることのなかった愛情を信じることはできないだろうし、信じたい気持ちもあって、心の中に葛藤が生まれるだろう。そして試しにわがままを言ってみる。おそらくエイダからしたら、そういうことなのだろう。ジェイミーのように本当の幼さからくる素直な甘え方が出来ないのだ。
少しずつ心を開き始めたエイダだったが、疎開先であるはずの村にも戦争の影が忍び寄る。そしてあの人も・・・。
人生とはたたかいだ。人は誰しも日々たたかっている。裏がえって安易にすら聞こえるこのような言葉も、それが実際に自分の身に降りかかってくる瞬間にそれは突如ずっしりとした肉体を持ち出す。肉体であろうが心であろうが私たちは深刻なダメージを受けるだろう。悲しみが心を満たし、ぼろ雑巾のように捨てられるかもしれない。それでも、私たちはたたかってみた方が良いのだろう。己のギアを入れるのだ。そうすれば優しさに出会える。一歩ずつでも踏み出せる。エイダの物語は、私たちにそう思わせてくれる力強さがある。
感想『黒い時計の旅』スティーブ・エリクソン著〜超弩級の読書体験がここにある!歴史if&パラレルワールドものの大傑作!!
歴史の源流に突如見たこともないほどのどす黒い血が流れだす。
人がそれほどの悪を、狂気を、死を
もたらすことができるなど、いったい今まで
ほんの少しでも
ほんの少しでも
考えてみたことがあった者などいたのだろうか?
赤毛の大男
バニング・ジェーンライト。
血塗られた出自を持ったその男。
彼がそのどす黒い血に触れたとき、世界は別の産声をあげた。
彼がその産声を聞いたとき、20世紀は二つに割れた。
彼のもとに二つの世紀から女が訪れ始める・・・。
一人目はアマンダだった。
二人目はモリー。
ローレン、ジーニン、
キャサリンにジャネットにリー。
だがドイツの兵隊が浮浪者を痛めつけている通りで
蝋燭店の上の窓から彼と目と目を合わせた瞬間に
二十世紀を分断させてしまったのはデーニアだった。
特別美人でもないその娘が踊るとどこかで人が死ぬ。
何故かはわからない。
何故かはわからないがバニングの書く文章に上顧客がつく。
バニングは彼のためだけにアマンダとモリーとローレンとジーニンと
いつの間にかいて、いつの間にか消えている彼女らと毎夜毎夜、
熱狂的な情事を繰り返す。そしてそれを大笑いしながら筆にする。
彼は彼の中の暴力を、大きすぎる暴力を感じる。
彼は生まれた家でその暴力によって腹違いの兄弟を、
父を、母を殺している。
彼もまた血塗られているのだ。
血塗られた指で血塗られた文章を書き、
それがまた、血塗られた眼によって熱狂的に読まれている。
そしてまた、歴史は分断される、
分断された歴史は、憎しみと悲しみと愛によって
復讐を誓われる。
その復讐を私たちが読むのだ。
感想『啄木歌集』久保田正文編〜〈歴史に残る無邪気・邪気〉一度でも 我に頭を 下げさせし 人みな死ねと いのりてしこと。

石川啄木の歌は他の誰とも似ていない。
誰でも共感できる体験を歌っているのに、誰にも真似することができないというのは実はとてつもなく凄いことだ。だけども啄木は別に偉い男ではない。むしろ駄目な男だ。だがそれを歌の世界では隠そうとしていない。そこが彼のいいところだ。
途中にて ふと気が変わり つとめ先を 休みて 今日(けふ)も 河岸(かし)をさまよへり。
わが抱く 思想はすべて 金なきに 因するごとし 秋の風吹く
彼の眼はとても澄んでいて、なんというか世に言う当たり前のことを当たり前と思ったりしないところがある。そこが多分、啄木の歌がもつ輝きの秘密だと思ったりもする。
ひと夜さに 嵐来たりて 築きたる この砂山は 何の墓ぞも。
砂山の 裾に よこたはる 流木に あたり見まはし 物言ひてみる。
水晶の 玉をよろこび もてあそぶ わがこの心 何の心ぞ。
或る時の われのこころを 焼きたての 麺麭(パン)に似たりと 思ひけるかな。
暮らしは貧しいが、その貧しさを歌の豊かさに変えている。
新しき インクのにおひ 栓抜けば 飢えたる腹に 沁むがかなしも。
うっとりと 本の挿絵に 眺め入り 煙草の煙 吹きかけてみる。
途中朝寝して 新聞読む間 なかりしを 負債のごとく 今日も感じる。
誤解を恐れず言えば、啄木の歌には馬鹿と紙一重の素直さがある反面、素直であるがゆえの邪気を孕んでいる。この邪気こそが啄木が永遠のトレンドたる由縁である。たぶん。
飄然(へうぜん)と 家を出でては 飄然と 帰りし癖よ 友は笑へど。
腕組みて このごろ思ふ 大いなる 敵目の前に 踊り出でよと。
人といふ 人のこころに 一人ずつ 因人がいて うめくかなしさ。
一度でも 我に頭を 下げさせし 人みな死ねと いのりてしこと。
啄木にちなんで、私もぢっと手を見てみた。なんだか蜘蛛みたいに見えて、面白い。
感想『モーターサイクルダイアリーズ』チェ・ゲバラ著〜人類史にのこるほどの革命家である彼が、もとは何処にでもいるような、夢見がちな、冒険好きな、向こう水な、一青年であったことに驚きを感じさせる一冊。本当にそこら辺にいそうな、少しばかり正義感の強いくらいの若者のユーモラスな青春旅日記。
エルネスト・チェ・ゲバラが革命家となる前。23歳の時の貧乏旅行記だ。医学生だった彼と、親友であるアルベルトは 冒険と、日常からの逃避のため、オートバイによる北米旅行を思いつく。そのときに書かれた日記をのちにゲバラ本人がものがたり風に書き改めたのが本書。
これは人を感心させるような偉業の話でもなければ、単なる「ちょっぴり皮肉な物語」でもないし、少なくともそれは僕の望むところではない。これは、願望が一致し夢が一つになったことで、ある一定の期間を共有することになったそのときの、二つの人生のひとかけらである。人間というものは、一生のうちの九か月間の間に、最も高尚な哲学的思索から、スープ一皿を求めるさもしい熱情にいたるまで、実にたくさんのことに思いを馳せられるもので、結局のところすべてはお腹の空き具合次第なのだ。
私は本書より先に、戸井十月著『チェ・ゲバラの遥かなる旅』を読んでいて、後年の彼やフィデル・カストロの凄さに圧倒されていたので、ゲバラ自身が上記のようなユーモアのある文章を書くのも意外だったし、本書を読んで彼が本当に普通の若者であったことに新鮮な驚きを感じた。・・・ところで、かれらが用意したオートバイだが実はとんでもなくボロくて、二人は死ななかったのが不思議なくらい何度もバイクから放り出されている。
かなりのスピードで走っている状態でやや急なカーブでブレーキをかけた時、リア・ブレーキの蝶ナットが吹っ飛んだ。カーブの先に一頭の牛の頭が、続いてたくさんの頭が現れた。僕がハンド・ブレーキをかけると、できの悪いこいつもこれまた壊れた。
バイクに乗ったアルベルトの後ろから、僕はアニメの映画みたいに、文字通り飛び出した。一つ一つのカーブが地獄のようだった。ブレーキ、クラッチ、一速、二速、お母さああああん。
ポデローサ(強力という意味)2号というこのバイクは、物語が半分もいかないうちに再起不能となっていて、中盤から旅の終わりまでは徒歩やヒッチハイク、密航で通している。だけど印象としては、どうしようもなく<モーターサイクル>であって、それ以外には考えられない。装丁も本書の雰囲気を過不足なく現していて素晴らしい。『モーターサイクルダイアリーズ』は偉大なる革命家の残したなんでもない青春の旅の記録で、金のない旅先でのパンのうまさ、その土地にくらす人びと、金をたかる、流れる景色、不安、わくわく、美しい自然、親切にもつきまとう蚊、何事にも打ち勝つ眠気、そんな、物語。ゲバラの娘、アレイダ・ゲバラ・マルチによるまえがきが、またイイ。
映画もまたイイ↓